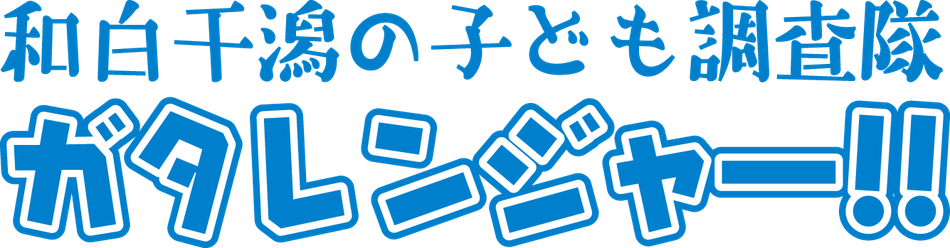第4回ガタレンジャー調査 唐の原川でアシ原調査

第4回ガタレンジャー調査
2018テーマ:生きものと環境の関係を学ぶ
日時:7月14日(土)14:00~17:00(干潮16:56/9cm)
集合場所:唐の原川河口 福岡県福岡市東区唐原2丁目
調査場所:唐の原川河口 周辺(干潟、アシ原)
参加者:ガタレンジャー12名(高校生2、中学生4、小学生8)+子供5、保護者6、スタッフ4+講師1/計28名
■前回の振り返り
3回目・五丁川河口の観察のおさらい。生き物と環境についての視点を確認。
カクベンケイガニは石積みに居た。ハクセンシオマネキは砂っぽくて少し硬い足が埋まらないような環境。
ハサニシャコエビは泥っぽい場所。干潟にはタマシキゴカイの巣がたくさんあった・・・など。
■唐の原川の左岸河口観察/環境の違いと生きものの違い。
唐の原川左岸に流れ込む小河川、アシ原を観察。最初はカニが逃げないように少し離れた場所から双眼鏡を使って観察。アシ原の周辺にアシハラガニをたくさん観察、泥っぽい場所ではヤマトオサガニを確認。少し近づいてアシ原の周りのハクセンシオマネキを確認しました。その後、実際に捕獲してそれぞれの特徴、オス・メスの違いなどを確かめました。他にトビハゼ、ケフサイソガニ、希少植物のシバナなどを確認しました。ハママツナを少しかじって塩分を確かめたりもしました。
昨年、ここのアシ原が清掃のために刈り取られてしまって、生物の生息環境が大きく劣化してしまいました。善意の清掃活動ではありますが、ここに希少生物がいることを知っていたら、他の対策があったかもしれないことを伝えました。
■干潟の泥&の中の生き物探し
休憩の後、干潟の高潮帯、低潮帯など4箇所で、泥を採集し、フルイで振るって、ピンセットを使って泥の中の生き物探しをしました。慣れないせいかあまり生物数は多くありませんでした。低潮帯ではアサリが多く見られましたが、高潮帯ではアサリは採取できませんでした。しかし、ミズヒキゴカイ、カワゴカイ、オキシジミなどが確認されました。また、ナナフシやヨコエビ類など普段観察できない小さな生物も観察できました。「ツツオオフェリア」の採取にもチャレンジしましたが、今回は空振りでした。次回再チャレンジしましょう。
■生き物チェック
とても暑い日でしたので、後半の生き物探しは、テントの中で実施しました。
今回は、環境や生物の説明に時間を多くとったので、確認した生物は24種類でいつもより少なかったようです。
■まとめ
今回は狭い範囲で、泥っぽい場所、砂っぽい場所、少し硬い砂礫混じりの場所、澪筋、小河川など様々な環境がコンパクトに揃っている場所で、それぞれの生き物の違いを意識しながら調査できました。
狭い範囲でも環境が違えば生物相が明らかに違うことに不思議さと興味を持つことができました。それぞれの環境に応じた生き物が生息していることを知ることで、いろんな環境を見る意識が向上していくことを期待できます。
見つけた生き物
《カニ・エビ類》
・フナムシ・アシハラガニ・コメツキガニ・ケフサイソガニ・ハクセンシオマネキ・ヤマトオサガニ・イソテッポウエビ・ハサミシャコエビ・エビ(不明/4cmくらい、赤っぽい色)・ヤドカリの仲間・ムロミスナウミナナフシ・ヨコエビ類
《カイ類/巻貝など》
・ウミニナ・ホソウミニナ・フトヘナタリ
《カイ類/二枚貝》
・アサリ・オキシジミ
《ゴカイの仲間》
・ゴカイ・ミズヒキゴカイ
《クラゲ、イソギンチャク、その他》
《魚類》
・マハゼ・ウロハゼ・ヒモハゼ
《植物》
・シバナ・ハママツナ・アシ
《鳥類》
25種類